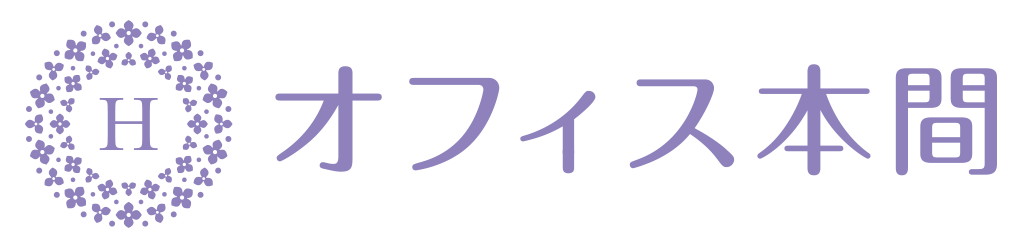大学院で就労支援政策の研究
就労困難者(障害者・ひきこもり等)とは
2024年4月から社会人大学院に在籍し、就労困難者に対する自治体の就労支援政策
について研究しています。
就労困難者とは、どのような人々のことを指すのでしょうか。
日本財団の就労困難者に関する調査研究によれば、
就労に何らかの課題・障害を抱えて無職、低賃金、不安定な就労環境等の状態に
なっている人を「就労困難者」と定義する。
出所:公益財団法人日本財団「就労困難者に関する調査研究」
とされています。
具体的には、病気や障害がある、ニート、フリーター、ひきこもり、ホームレス
依存症、刑余者などです。これらの人々は、働きたくても働けない、あるいは
働いても低賃金や不安定で生活が困窮するという課題を抱えています。
そのため、2015年に施行された「生活困窮者自立支援制度」では、地方自治体は直ちに
一般就労を目指すことが困難な人々を対象に就労準備支援や就労訓練などの事業を実施
することができるとしています。
我が国においては、長らく雇用政策は国の事業であるとされてきました。
ですが、2000年の地方分権一括法の改正により、地方自治体は地域の実情に沿った
政策を展開することが可能となり、無料職業紹介など自治体独自の就労支援を実施できる
こととなったのです。
ただ、これまで雇用政策の経験がない自治体には、就労支援のノウハウやスキルが蓄積
されておらず自ら実践するには高いハードルが存在するため、多くの自治体では民間への
委託などに頼らざるを得ない状況にあります。
そのような中であっても、積極的に就労困難者の就労支援に取り組む自治体も存在して
います。研究機関と連携して主に障害のある就労困難者への就労支援を実施したり
条例を制定して就労困難者への支援や雇用を生み出す施策を実現させたり、そのための
財源確保や支援の工夫などを重ねている自治体が増えています。
その背景には、多様性社会と地方を始めとした人手不足の問題があると言われています。
人口減少時代に突入した日本においては、かつてのように、男性正社員が長時間労働や
転勤なども厭わず終身雇用で働くというような同質性の高い状況ではなくなりました。
必要な労働力を確保するためには、女性・高年齢者外国人等を積極的に活用していかな
ければならないですし、障害者の法定雇用率を守るために障害がある労働者へ配慮しつつ
安定して働けるような環境も作っていかなければなりません。
同質性の高い職場であれば、労務管理もしやすかったと思いますが、ワークライフバランス
を重視する姿勢は若い男性社員にも浸透してきていますし、長時間労働が難しい労働者が
働きやすい職場は誰にとっても働きやすい職場になるとも言われています。多様な人々が
プライベートな時間を確保することで、心身共に健康で働き続けるための施策が重要な
経営戦略となってきているのです。
そうは言っても、就労困難者への就労支援は公的な機関でなければ難しい状況にあります。
今後法改正によって障害がある方への就労支援のみならず、全ての就労困難者への就労支援が
実現するまでは、地方自治体による就労支援政策が推進されることが望まれます。
そのためには、どのような方策が効果的であるのかについて研究し、その成果を修士論文に
まとめたいと思います。